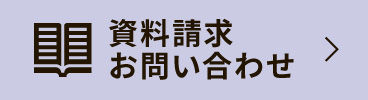「直葬ではどんな服を着ればいいの?」「カジュアルな服装でも大丈夫?」といった疑問をお持ちではないでしょうか?
直葬は、近しい親族のみで行われる葬儀形式のため、「喪服は必要ないのでは?」と考える方もいるかもしれません。
しかし、直葬だからといってマナーを無視した服装は避けるべきです。
本記事では、直葬にふさわしい服装について詳しく解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。
直葬での服装について
直葬の服装について確認していきましょう。
・男性の服装
・女性の服装
・子供の服装
・平服を指定された時の服装
・家族のみの服装
男性の服装
男性は準喪服として黒のスーツを着用します。シングルでもダブルでも構いませんが、光沢の少ない黒を選び、柄や色付きのものは避けましょう。
ワイシャツは白が基本ですが、無い場合はグレーでも可能です。ネクタイ、靴、靴下は黒で統一し、ネクタイピンや金具付きの靴、光沢のある装飾品は外すのが適切と言われています。
また、動物の皮を使用した小物は避け、控えめな装いを心掛けるとよいでしょう。
女性の服装
女性の服装は、準喪服や略喪服のワンピース、スーツ、パンツスーツ、アンサンブルなどを着用します。色は黒を選び、スーツのインナーには白のシャツや、落ち着いた白や黒系のブラウスを合わせるとよいでしょう。
生地はシンプルで、光沢が少なく透けにくいものを選び、スカートは長めの丈が望ましいです。ストッキング、靴、バッグも黒で統一します。
また、装飾品は基本的に控えめにし、身につける場合は真珠のネックレスやイヤリングを選ぶとよいでしょう。
子供の服装
子供の服装は特別に喪服を用意する必要はなく、学校の制服で問題ありません。
制服がない場合、喪服と揃える必要はなく、黒やグレーなど落ち着いた色の服装を選びましょう。派手な色や光沢のある素材、目立つデザインを避ければ問題ありません。
礼服を着用する場合、男の子はブレザーとズボン、女の子はブレザーとスカート、またはワンピースが適しています。女の子の服は、刺繍やフリルなど装飾の多いものは控えましょう。
基本的なマナーは大人と同じであるため、靴や靴下にも注意し、落ち着いた色合いのものを選ぶことが大切です。
乳幼児の服装も同様に、黒や紺など落ち着いた色を基調とし、無地のシンプルなデザインを選びましょう。喪服である必要はありません。
また、長時間の参列が難しい場合や騒がしくなることが心配な場合は、知人に預けるのも一つの選択肢です。
平服を指定された時の服装
直葬の案内状に「平服でお越しください」と記載されている場合、基本的には略喪服で参列するのが適切と言われています。
男性はブラック・グレー・紺のダークスーツ、女性はブラック・グレー・紺のワンピース・アンサンブルやスーツ、パンツスーツが該当します。黒を基調とした落ち着いた服装を選び、基本的なマナーを守りましょう。 なお、「平服=カジュアルな服装」とは限らないため、過度にラフな格好は避けましょう。
家族のみの服装
家族のみで火葬を行う場合、必ずしも喪服を着る必要はありません。
ただし、マナーを考慮し、黒などの落ち着いた色を基調とした、できるだけ控えめな平服を選びましょう。
また、同居していない家族が参列する場合は、服装の統一感を持たせるため「平服で」と伝え、事前に相談しておくと安心です。
直葬で気を付けるべき身だしなみ
直葬で気を付けるべき身だしなみとして、以下が挙げられます。
・きらびやかで派手な服装は控える
・メイクは控えめにする
・髪は基本的に黒色にする
きらびやかで派手な服装は控える
直葬では、派手な服装は控え、落ち着いた装いを心がけましょう。
男女問わず黒を基調とした服装を選び、鮮やかな色や派手な柄は避けるのがマナーです。デザインは無地でシンプルにし、靴やネクタイ、靴下も黒で統一するとよいでしょう。
また、毛皮や蛇革など殺生を連想させるもの、露出の多い服装、カジュアルすぎる服装も不適切とされます。
直葬であっても故人への敬意を示す服装を選び、火葬場では周囲の人にも配慮し、目立たないようにしましょう。
メイクは控えめにする
直葬では服装だけでなく、メイクも控えめにすることが大切です。葬儀では「片化粧」と呼ばれる、色味を抑えたメイクが基本とされています。
特に口紅の色味や光沢は抑えるのが一般的です。仕上げすぎると華やかになり、良くない印象を与える可能性があるため、避けるのが無難ですが、ノーメイクはマナー違反とされるため、派手にならない程度に整えましょう。
なお、「片化粧」と「ナチュラルメイク」は異なるものなので、その違いを理解した上で適切なメイクを心がけましょう。
髪は基本的に黒色にする
直葬では、髪色は基本的に黒色が望ましいです。 暗めの茶髪であれば許容されますが、明るすぎる場合は黒染めやスプレーで調整するとよいでしょう。
髪型は、顔にかかる長さなら耳より下でまとめましょう。
男性がスタイリング剤を使う場合は光沢の少ないドライワックスが無難です。女性は、派手なアクセサリーや飾りの多いアップスタイル、リボンなどは避けましょう。
見落としがちな気を付けるべき直葬のマナー
見落としがちな気を付けるべき直葬のマナーとして、以下が挙げられます。
・アクセサリーは基本的に付けない
・ネイルは落としておく
・香典の有無について確認する
アクセサリーは基本的に付けない
直葬では、基本的にアクセサリーの着用は控えるのがマナーとされています。特に、華美な装飾や光沢のあるものは避け、落ち着いた装いを心がけましょう。
ただし、結婚指輪は外す必要がなく、女性であれば一連の真珠のネックレスに限り着用が許されます。ただし、二連のネックレスは「不幸が重なる」とされるため、避けるのが望ましいです。
一方で、イヤリングやピアス、男性の金属製の腕時計やネクタイピン、装飾が目立つものなど、華やかな印象を与えるアクセサリー全般は控えましょう。
また、髪をまとめる際は、黒のヘアゴムやヘアピンなど、目立たないものを選ぶとよいでしょう。
直葬では、故人を静かに見送ることが何より大切です。派手な装いを避け、慎みのある身だしなみを意識しましょう。
ネイルは落としておく
直葬の場合、ネイルは装飾品と同様の扱いとなるため、事前に落とすのが望ましいです。これは、故人への敬意を示すとともに、参列者全体が控えめな服装で臨むための基本的なマナーです。
例えば、マニキュアやネイルチップ、ジェルネイルなどは、家庭用のアセトンフリーのリムーバーを利用すればセルフケアが可能な場合があります。 もし自身での処理が難しい場合は、ネイルサロンでのオフ処理を依頼する方法もあります。
香典の有無について確認する
直葬では基本的に近親者のみが参列するため、香典は不要とされています。ただし、遺族の意向によって異なるため、事前に確認しておくと安心です。
遺族側から「辞退する」と明確に伝えられた場合、持参する必要はありませんが、特に案内がない場合は、気持ちとして用意しておくのが無難です。また、地域や家庭によって考え方が異なるため、周囲の方にも確認しておくとよいでしょう。
参列者の中には、どうしても香典を渡したいと考える方もいるかもしれません。その場合は、遺族や喪主に直接手渡しするのが適切です。 渡すタイミングとしては、集合時や解散時は慌ただしくなるため、火葬を待っている間など、落ち着いた時間を選ぶのが望ましいでしょう。
直葬の服装に関連するよくある質問
喪服が準備できない時はどうすれば良いですか?
喪服を用意できない場合でも、平服で参列することは可能です。
その際は、無地の黒を基調とした落ち着いた服装を選びましょう。仕事帰りに直接向かう場合は、私服や作業着、ビジネススーツでも問題ないとされています。
また、喪服の一日レンタルサービスを利用する方法もあります。状況によっては、親しい友人から借りるのも一つの手段です。可能な範囲で故人や遺族に配慮した服装を心がけましょう。
直葬で持っていくべきものはありますか?
直葬に参列する際の持ち物として、以下のものを準備しておくと安心です。
・ハンカチ
・ティッシュ
・スマートフォン
・財布
・香典(求められた場合)
特別な持ち物は必要ありませんが、最低限のものは用意しておきましょう。ハンカチは華美なものを避け、シンプルで落ち着いた色合いのものを選ぶのが望ましいとされています。