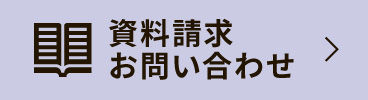「直葬でもお布施は必要?」「直葬でお布施を渡す場合の相場を知りたい」といった疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。
本記事では、直葬でお布施を渡す必要があるのかどうかをはじめ、お布施の相場、戒名に関すること、お布施を渡す際のマナーまで、詳しく解説していきます。
上記のようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ最後までご覧ください。
直葬でお布施は必要?
そもそもお布施とは、僧侶に対して感謝の気持ちを表すために渡すお金です。そのため、直葬であっても僧侶を呼ぶ場合には、お布施が必要になります。
たとえば、読経を依頼したり、戒名を授かる際には、通常の葬儀と同様にお布施が発生します。ただし、直葬は参列者が少なく香典収入も期待できないため、その費用は遺族負担になることが多い点に注意が必要です。
一方で、僧侶を一切呼ばず、家族だけで火葬を行う場合は、お布施は必要ありません。ただし、後日お寺に納骨する際などには、別途お布施が必要になることもあります。
このように、直葬でお布施が必要かどうかは、「僧侶の関与があるかどうか」によって決まります。事前に確認しておくと安心です。
お布施の相場
お布施には明確な金額の決まりはなく、一般的には「お気持ちで」と表現されます。とはいえ、実際には相場が存在します。
直葬で僧侶に読経を依頼する場合、読経料としてのお布施の相場は3万円〜30万円程度と言われています。金額は、都市部か地方かの違いや、宗派や寺院の方針などによって異なります。
また、交通費が別途かかる場合は「お車代」として5,000円〜1万円程度を包むのが通例です。さらに、葬儀の場ではなく、後日の納骨時に読経をお願いする場合でも、同程度の金額が目安とされます。
寺院によっては具体的な金額を教えてくれる場合もあるため、心配なときは遠慮なく相談すると安心です。
戒名を付ける際の相場
直葬であっても、戒名を希望する場合は、僧侶に依頼して授与してもらう必要があります。
お布施の相場は、戒名の「位(くらい)」によって大きく異なります。もっとも一般的な「信士(しんし/しんじ)・信女(しんにょ)」で10万〜30万円程度。
「信士・信女」の一段上の「居士(こじ)・大姉(だいし)」になると、30万〜50万円ほどが目安です。
さらに格式の高い「院号」が付く戒名を希望する場合は、50万円以上かかることもあり、寺院によっては100万円を超えるケースもあります。
直葬でお布施を渡す際のマナー
直葬でお布施を渡す際のマナーとして、以下が挙げられます。
・白い封筒でお布施を包む
・濃墨で表書きをする
・お盆にのせるか袱紗(ふくさ)に包む
白い封筒でお布施を包む
お布施を包む際は、無地の白い封筒や奉書紙(ほうしょし/ほうしょがみ)を使用するのが一般的です。
封筒を選ぶ場合は、郵便番号の枠や模様がないシンプルなものを用いましょう。より丁寧にしたい場合は、現金を半紙や白い中袋で包み、その上から奉書紙で包むことで、格式が高まります。
なお、水引付きの不祝儀袋を用いるケースもありますが、地域や宗派によって異なるため、確認が必要です。
濃墨で表書きをする
封筒の表書きは、濃墨の筆や筆ペンを使い、丁寧に記入するのが基本です。表の上部中央には「御布施」または「お布施」と書き、その下には施主のフルネーム、もしくは、仏事を行った家の名前を「○○家」と記載します。
金額を記入する場合は、封筒の裏面や内袋の表面に、旧字体(大字)を用いて「金壱萬円」といった形式で記載します。あわせて、住所を記載する際は、内袋の裏面に記入するのが一般的です。
お盆にのせるか袱紗(ふくさ)に包む
お布施を僧侶にお渡しする際には、直接手渡しするのではなく、小さなお盆(切手盆や祝儀盆)にのせて差し出すのがマナーです。
お盆が用意できない場合は、袱紗(ふくさ)に包んで持参し、渡す際には袱紗の上にお布施をのせて差し出します。葬儀の場面において袱紗の色は、寒色系や紫色が適切とされています。また、お布施をお渡しするタイミングは、僧侶が到着された際や読経の前後が一般的です。
直葬でお坊さんを呼ぶ方法
直葬でお坊さんを呼ぶ方法として、以下の方法が挙げられます。
・菩提寺に相談する
・葬儀社に相談する
・地域の寺院に相談する
・僧侶の派遣サービスに相談する
菩提寺に相談する
菩提寺がある場合、まず最初にその寺院に相談することが重要です。
直葬を希望する旨を伝え、お坊さんに読経や戒名の授与をお願いできるかを確認しましょう。ただし、菩提寺によっては直葬に対して理解が得られない場合もあるため、事前の相談が不可欠です。
また、読経や戒名の授与に関する費用(お布施)についても、菩提寺に直接尋ねることで明確になります。
一般的には、読経や戒名の授与には一定のお布施が必要となりますが、具体的な金額は寺院や地域によって異なります。
葬儀社に相談する
菩提寺がない場合や、特定の寺院との付き合いがない場合は、葬儀社に相談する方法があります。
多くの葬儀社は、僧侶の手配サービスを提供しており、直葬においてもお坊さんを手配することが可能です。
葬儀社に依頼する際は、希望する宗派や読経の有無、戒名の授与など、具体的な要望を伝えることで、適切な僧侶を紹介してもらえます。
また、葬儀社を通じてお坊さんを手配する場合、費用が明確に提示されることが多く、予算に応じた選択がしやすくなります。
地域の寺院に相談する
近隣の寺院に直接相談する方法もあります。
地域の寺院に連絡を取り、直葬での読経や戒名の授与をお願いできるかを尋ねてみましょう。寺院によっては、檀家でなくても対応してくれる場合があります。
ただし、寺院によっては直葬に対する考え方が異なる場合があるため、事前の打ち合わせが必要です。
また、読経や戒名の授与に関するお布施の金額も寺院によって異なるため、事前に確認しておくことが望ましいです。
僧侶の派遣サービスに相談する
近年では、インターネットを通じて僧侶を派遣するサービスも増えています。
これらのサービスを利用することで、宗派や地域を問わず、お坊さんを手配することが可能です。
これらのサービスでは、希望する宗派や日時、場所などを指定して依頼することができ、費用も明確に提示されている場合が多いため、安心して利用できます。
ただし、サービス提供エリアが限られている場合があるため、事前に対応可能かを確認することが重要です。
「直葬でお坊さんを呼ぶ・呼ばない」に関連する質問
直葬で戒名は必要ですか?
直葬を選ぶ場合、戒名を授かることは一般的ではありません。
戒名は仏教の儀式の一部として、仏教徒の死後に供養のために授与されますが、直葬の場合は、仏教儀式を省略することが多いため、戒名を必要としないケースが増えています。
ただし、故人や遺族が希望する場合には、戒名を授かることもできます。この場合、仏教寺院に依頼することになりますが、直葬を選んだ場合でも戒名を受けるかどうかは個人の選択によります。
直葬は後悔しませんか?
直葬を選ぶことで後悔するかどうかは、遺族の考え方や価値観に依存します。
直葬は、経済的負担や時間的制約を減らすことができる選択肢として人気がありますが、一方で、伝統的な葬儀を省略することで、心の整理や供養の部分で不安を感じることもあるかもしれません。
事前に故人や遺族がどういった形で見送ることが理想的かを話し合い、決定することが重要です。直葬を選んでも、後から供養を行ったり、お寺で法要を行うことが可能な場合もありますので、柔軟に対応できる選択肢も存在します。