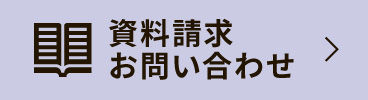「直葬と火葬式の違いを知りたい」「各葬儀形式と直葬・火葬式の違いが気になる」と感じている方も多いのではないでしょうか。
本記事では、直葬と火葬式の違いをはじめ、各葬儀形式との違いや、直葬ならではのメリットについて、わかりやすく解説しています。
こうしたお悩みをお持ちの方は、ぜひ最後までご覧ください。
火葬式とは?直葬や家族葬との違いを解説
直葬と火葬式は、基本的に同じ意味として扱われることが多く、どちらもお通夜や告別式を省略し、火葬のみを執り行う葬儀の形です。
ただし、葬儀社によっては「弔いの儀式を一切行わないものを直葬」、「仏教式の儀式を取り入れたものを火葬式」と区別している場合もあります。
いずれもほとんど同じ意味合いで使われるため、本記事では「直葬(火葬式)」という表現で統一してご紹介していきます。
以下は、主な葬儀形式になります。
・直葬(火葬式)
・家族葬
・一般葬
・社葬・合同葬
・密葬
直葬(火葬式)
直葬は、通夜や告別式といった儀式を省き、火葬のみを行う葬儀です。火葬式とほぼ同じ意味で使われることもありますが、葬儀社の扱いによっては、細かな違いが見られる場合もあります。
直葬(火葬式)では、参列者が限定されるため、故人と親しかった人々が最期のお別れをする場を失ってしまうケースも少なくありません。そのため、火葬後にあらためて自宅や会場でお別れの機会を設けるなどの対応が行われることもあります。
家族葬
家族葬は、身内や親しい友人など、ごく限られた人々のみで執り行う葬儀です。
一般的な葬儀と同様に通夜や告別式を行いますが、参列者を絞ることで、故人との時間を静かに過ごせるのが特徴です。
参列者の数が少ないため、一般葬に比べ、費用軽減が期待できますが、葬儀に参列できなかった方が後日弔問に訪れるケースもあるため、その点を考慮する必要があります。
また、家族葬を選ぶ際には、故人の交友関係や親族の意向などを事前にしっかり確認しておくことが大切です。
一般葬
一般葬は、故人と関わりのあった幅広い人々が参列する、最も標準的な葬儀の形式です。通夜、告別式、そして火葬といった一連の流れを踏みながら、多くの参列者が故人との別れに立ち会います。
規模が大きくなりやすいため、準備や運営に時間と費用を要する傾向がありますが、故人の人間関係を色濃く反映できる点が特徴です。
ただし、大勢の対応や儀式進行の負担が遺族にとって大きくなる場合もあり、あらかじめ計画を立て、必要に応じて専門家のサポートを受けることが求められます。
社葬・合同葬
社葬は、企業や団体が主体となって執り行う葬儀です。故人がその組織において重責を担っていた場合などに実施されます。
一方、合同葬は複数の組織や団体が協力し、共催という形で行う葬儀を指します。
これらの形式はいずれも参列者の数が多く、大規模になることから、事前の綿密な準備や関係者との調整が必要になります。
故人の功績や人物像を社会に広く伝えるため、式典内では映像やスピーチなどを用いた演出が行われることもあり、場合によっては報道機関の取材が入ることもあります。
そのため、遺族や主催者には公的な場面での対応が求められ、個人葬とは異なる配慮や進行が必要となります。
密葬
密葬は、遺族やごく親しい関係者だけで執り行う、私的な葬儀の形式です。特に故人が著名人である場合や、諸事情により公に知らせたくないときに選ばれることがあります。
一般的な参列者を招かず、静かな環境の中で故人と向き合えるのが特徴です。
密葬の後には、本葬やお別れの会などを改めて開き、広く関係者とお別れの機会を設けることもあります。この形式を選ぶことで、遺族は外部の干渉を受けず、落ち着いて故人を見送る時間を確保できます。
ただし、参列できなかった人々への配慮が求められる場面もあり、後日弔問や供花の申し出があった際には、丁寧な対応が必要になることもあります。
直葬・火葬式のメリット・デメリット
直葬・火葬式のメリット・デメリットを確認していきましょう。
直葬(火葬式)のメリット
直葬(火葬式)のメリットとしては、以下が挙げられます。
・葬儀費用を抑えられる
・短い時間で終えられる
・参列者への対応が少なく済む
中でも一番のメリットは、葬儀にかかる費用を大幅に抑えられることでしょう。一般的な葬儀に比べて、通夜や告別式といった儀式を省くことで、費用の負担を大幅に減らすことが期待できます。
経済的な理由からシンプルな見送りを希望されるご遺族にとっては、大きなメリットになるでしょう。
また、短時間で葬儀を終えられる点も、直葬(火葬式)ならではの特徴です。準備に時間や手間をかけずに済むため、忙しい日々を送っている方や、突然のことで対応に追われるご遺族にとっても負担が少なくて済みます。
加えて、参列者への対応や挨拶まわりといった気遣いが必要ないことも、大きなメリットのひとつです。大切な人を失って心が追いつかない中でも、最低限の流れで静かにお別れができることで、精神的な負担を少しでも軽くすることができるでしょう。
直葬(火葬式)のデメリット
直葬(火葬式)のデメリットとして、以下が挙げられます。
・菩提寺に納骨を断られる可能性がある
・親族の理解を得られない場合がある
・お別れの時間が短くなる
まず、代々菩提寺に納骨している場合、宗教的な儀式を省略する直葬では、納骨を断られるケースがあります。菩提寺によっては、通夜や告別式を行わないことを受け入れていない場合もあるため、事前の確認が必要です。
また、親族の中には、特に高齢の方を中心に、宗教的な儀式を大切に考える方も多くいます。
そうした方々からは、「故人に失礼ではないか」「ちゃんと弔ってあげられたのか」といった不満の声が上がることもあるかもしれません。理解を得るためには、事前の説明や話し合いが欠かせません。
さらに、直葬(火葬式)は短時間で済ませられる反面、故人と過ごすお別れの時間が限られてしまうという側面もあります。
心の整理がつかないままお別れを迎えてしまうこともあるため、その点も踏まえて判断することが大切です。
直葬のメリットとデメリットの両方をしっかりと理解し、ご家族や親族とも話し合った上で、納得のいく形を選ぶようにしましょう。
直葬・火葬式・家族葬の料金形態に違いはある?
直葬(火葬式)の場合
費用の内訳としては、遺体の搬送や安置にかかる費用、棺や骨壺など最低限必要なものが中心になります。
火葬場の使用料を含めても、一般的には20万円から40万円ほどで済む場合が多く、葬儀社によっては10万円台のプランを提供しているケースもあります。
費用が安いというメリットがありますが、通夜や告別式といった儀式がない分、後になって「きちんとお別れできなかった」と悔いが残ることや、親族や友人に十分な弔問の機会を設けられないといったデメリットもあります。
そのため、事前に家族の中で十分に話し合い、納得したうえで選択することが大切です。
家族葬の場合
家族葬の費用については、全国的な平均でおよそ105万程度※とされており、葬儀一式の費用に加えて、飲食や接待、寺院へのお布施なども含まれるのが一般的です。
家族葬の大きな魅力は、遺族が慌ただしくならずに、故人と静かに向き合える点です。対応する参列者が限られているため、精神的な負担も比較的軽く済むでしょう。
一方で、参列を希望していた方への配慮が必要になることもあり、葬儀後に弔問客が訪れるケースもあります。
※参照元:第6回お葬式に関する全国調査(2024年/鎌倉新書)
直葬(火葬式)を行う際の注意点
直葬(火葬式)を行う際の注意点として、以下が挙げられます。
・菩提寺への確認
・家族・親族との話し合い
・費用の確認
・故人の安置場所の確保
菩提寺への確認
直葬(火葬式)を行う際の注意点として、菩提寺への確認を行いましょう。
葬儀を省略したことを理由に、菩提寺が納骨を拒否する場合があります。特に先祖代々の墓が菩提寺にある場合、納骨を拒まれるとその後の供養に支障が出ることもあるため、注意が必要です。
直葬を検討している段階で、必ず菩提寺に相談しましょう。
家族・親族との話し合い
直葬(火葬式)を行う際の注意点として、家族・親族との話し合いを行いましょう。
特に高齢の親族の中には、「葬儀はきちんと行うべきだ」「通夜や告別式を通じて故人とお別れするのが礼儀だ」と考える方も多くいらっしゃいます。
突然、直葬を決めてしまうと、家族間でのトラブルや誤解を招く恐れがあります。直葬(火葬式)を選ぶ理由を丁寧に説明し、家族一人ひとりの気持ちにも寄り添いながら話し合いを進めることが大切です。
費用の確認
直葬(火葬式)を行う際の注意点として、費用の確認を行いましょう。
直葬(火葬式)は、通夜や告別式、会食などを行わないため、一般的な葬儀に比べて費用を大きく抑えられる傾向があります。
ただし、「すべてが安く済む」というわけではありません。実際には、直葬(火葬式)でもおおよそ20万から40万円程度の費用がかかると言われています。棺や火葬料、搬送費、安置費など、必要最低限の項目だけでも一定の出費は避けられません。
そのため、事前に複数の葬儀社から見積もりを取り、全体の費用をしっかり把握しておくことが大切です。
故人の安置場所の確保
直葬(火葬式)を行う際は、故人の安置場所の確保に注意が必要です。
日本の法律では、死亡後24時間以内の火葬が禁じられているため、直葬(火葬式)であっても亡くなってすぐに火葬することはできません。必ず一時的に故人を安置する場所を用意する必要があります。
自宅で安置することも可能ですが、住宅環境や家族の事情によっては難しい場合もあります。そのようなときは、葬儀社の安置施設や民間の遺体安置施設を利用するのが一般的です。
これらの施設は事前予約が必要な場合もあるため、早めに安置場所を確保し、費用の確認もしておくと安心です。
直葬・火葬式での服装
直葬・火葬式であっても、基本的には一般的な葬儀と同様に喪服を着用するのが望ましいとされています。
男性は黒のスーツに白いシャツ、黒のネクタイ、黒の靴下と靴を着用します。女性は黒のワンピースやスーツ、肌色のストッキング、黒の靴が一般的です。
ただし、直葬や火葬式は遺族や親族のみで執り行われることが多く、参列者が限られるため、服装に関しては柔軟に対応されることもあります。
例えば、故人や遺族の意向で「平服(普段着)でお越しください」と案内されることもあります。その場合は、派手な色やデザインは避け、落ち着いた色合いの服装を選びましょう。
また、地域・宗教・家庭の慣習によっても服装マナーは異なるため、事前に確認しておくのが安心です。特に指定がなければ、一般的な喪服を選ぶと失礼がありません。
「直葬と火葬式の違いとは?」に関連する質問
直葬(火葬式)が増えている理由は何ですか?
直葬(火葬式)が増えている背景には、いくつかの理由があります。
まず挙げられるのが、経済的負担の軽減です。従来の葬儀では通夜や告別式、会食など複数の儀式があり、費用も高額になりがちです。一方、直葬(火葬式)はこれらを省き、火葬のみを行うため、費用を大きく抑えることができます。
次に、社会構造の変化があると言われています。核家族化や高齢化が進む中で、親族や知人が少なく、大規模な葬儀を行う必要がないケースが増えています。
また、故人や遺族の意向として、形式にとらわれず、静かに見送りたいと考える人も増加しています。こうした経済的・社会的・個人的な理由が重なり、直葬(火葬式)を選ぶ人が年々増えていると言われています。
直葬(火葬式)では香典が必要ですか?
直葬(火葬式)では、基本的に香典は必要ないとされることが多いです。
ただし、遺族が香典を辞退していない場合は、念のため持参しておくと安心です。その際は、一般的な葬儀と同様に、不祝儀袋を用い、薄墨で氏名や金額を記入し、適切な金額を包みます。
一方で、遺族から香典辞退の意思が示されている場合は、その意向を尊重し、無理に渡さないようにしましょう。
直葬(火葬式)を選択する人の割合はどの程度ですか?
直葬(火葬式)を選択する人の割合は9.6%※という調査結果が出ています。
この背景には、前述の経済的負担の軽減や社会的変化、故人や遺族の意向などが影響しています。また、葬儀に対する価値観の多様化も一因と考えられます。